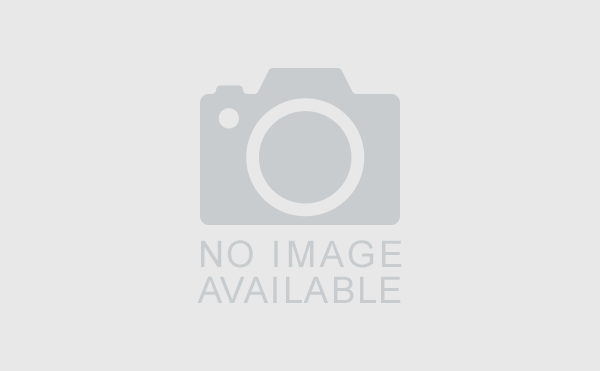2025年4月25日①午後の部:GLP昭島プロジェクト造成工事施工計画に関する説明会
昨日は、GLP昭島プロジェクト造成工事施工計画に関する説明会が午後・夜と開催され、両方参加してまいりました。
https://drive.google.com/file/d/1FhZSeJwvyGQKRM7MQq-OVbWEQ7WbpYtM/viは
工事内容は
・造成工事(建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成)
・道路工事
・建築等解体工事(昭和館、クラブハウス、第二練習場、棒球ネット・支柱等撤去)
今回説明あった工事内容の予定工期は、2025年6月下旬から2026年6月下旬の約1年間で、
その後建築工事は2026年6月下旬~2028年12月末頃予定とのこと。
その他詳細については、昨日配布資料は今後以下から公開されると思われます。
https://glp-akishima.net/news
質疑でとくに多くでた意見は、「地域住民との協議をしている最中の工事着手強行は不誠実。住民意見を聞く気はあるのか」というもの。
東京都の環境影響評価審議会・都知事が事業者に重要課題と指摘する、「市民との信頼関係の構築」に水をさし、一層不信感が増していると捉えざるをえない状況でした。
書き取れなかった場面もあり、以下、正確でない部分もあるかと思いますが、質疑ででた意見趣旨となります(「→」あとは事業者答弁)。
●つつじが丘自治会では2月に意見交換会があり、次の約束もした。他地域でも協議が実施され継続。これから協議をされる地域があるにも関わらず工事説明するのは不誠実。
発生交通量がデータセンターの環境影響についても資料詳細が明らかになっていないものもある。子どもの未来を心配するとともに、市の計画で位置づける水と緑が失われることに対し、不誠実で住民を裏切っているといわざるをえないと意見。
なぜ1日片道5,800台の発生交通量なのか。
→規模から単位面積あたりの台数を割り出す。交差点の現状調査をし、台数をプラスして交差点が大丈夫か確認。
●つつじが丘北自治会では、説明会が開かれていない。終わらないうちの工事説明は順番が逆と意見。
①3年間聞いているが、樹木を何本切って何本残すのか回答がない。
②持続的な会社経営、持続的な社会を企業理念にあげているが、データセンターの環境影響と持続可能性との整合性について、今回説明がない。
→①樹木については、環境アセスメントの評価書でも記載したが、正確な本数はもっていない。伐採する際には移植の範囲を決めて緑率を確保する。
②データセンターは大きな電力を使うが、生活を支えるために必要。
電力消費で周囲の電力が足りなくなることはない。
CO2発生については、そのまま建物からでるのではなく火力発電で計算されるものであり、電力を置き換えることが大事。
●武蔵野でまち工場を経営。過去も説明会開催案内遅く、これないときもあった。前から会場確保し決まっているならば説明会は早く案内すべきと意見。
①これまでの回答含めた議事録を公開すべき。
②瑞雲中の西は交通課題対処が示されているが、東に右折レーンがあってほしい。
→①よくある質問、考えは掲載していく予定。本日の内容をまとめたものも載せていく。
②意見は行政に伝える。可能なことがあれば検討。
●東京都環境アセスメント手続きの審議会・都知事意見でも住民の不安が払拭されていないとされた。各地で説明会を開いているが決着していない。この状況での説明会実施は住民の不信感を大きくさせる。進め方を見直すべきと意見。
①住民の立場から、公害紛争調停を都に申請しているが、5月9日までにGLPから回答がでる予定。申請内容には、協議が決着するまで着工しないでほしいというものが含まれているが、拒否の意思表明であるのか。
②GLPのサスティナブルポリシーと相反するのではないかとGLPグローバル担当と経営陣に公開質問状を送付したが、回答はおろか受理確認も届いていない。状況と今後の対応は。
→①調停はお互いに公表しないものと聞いており、回答は調停の場とする。
②公開質問状は認識している。内容を確認し、回答する。
●都道220号線近い松原町に在住。太陽子ども病院西から消防署前について、対応は充分なのか(配布資料p36,38で滞留長が違うのは不自然ではないか)。
→車両が増えることで、一部右折滞留長が伸びる。交差点で対応できるところは対応する。
また、交差点で増える台数はまちまちとなる。
●流山にあるGLP物流センターとの決定的な違いは、昭島はほとんどが住宅地で道路がすべて狭いことであり、ここに施設をつくることは地域に対する暴挙である。地域との共生といっているが、納得する説明がないまま今日にいたり、全く信じられない。地域との共生に地域住民は入らないのか。我々を除いてどこと共生するのかと意見。
また、いくつかの交差点の滞留長を伸ばすというが、計画地から離れており敷地外である。なかには交差点の形状まで変えるものもある(配布資料p39)。敷地と関係ない道路のレーンを変えたり交差点の形状までかえるのは何の権限があるのか。
→市道は市、都道は都に対し、工事前には計画をし了解とる。滞留の許可はとっていない。あくまでGLPが計画している内容について説明している。
・大丈夫でないから、まだ決まってもおらず行政との協議すらしていない対策に今回言及しているのではないか。
→全体の交差点がパンクしないようにしている。2023年11月に交差点需要率が大きく変わらないと説明したとはいえ、地域の不安の声があり、必要かつ改良できるものはする。こういう協議が整ってきていると、過去の内容の続きを説明した。
・信用できない。
●諏訪松中通りの交通渋滞を心配しているが、怒っていて我慢ならない。2月22日に自治会ブロックと保護者有志で協議をした。いろいろな議論があったが、発生交通量1,1600台は減らしてもらえないのか。データセンターのCO2も再エネで解決というが、量を克服できるデータや説明は示されていない。カーボンニュートラルとの整合はとれるのか。自治会・市民を納得させるには、見通しを明確にしてほしい。発生交通量以外にも、保護者からは入出庫の時間を変更できないかという要望もある。本当に不安で心配。市の一車線道路は自転車が怖くて走れないが、道路交通法が変わり歩道を走れば罰金と報道されている。これまで検討などといっているが、責任ある回答がなく、社長からの明確な回答が欲しい。
→物流施設6棟から3棟に集約した際にも台数は変えず。面積から割り出す。ここで100~200台減らすというほうがのちのち考えると不誠実。また、2023年11月の説明会で、物流施設は8時台の車は通勤車両が5割でこれを減らす手立てをしたいとはなした。システムの検討は相模原でも試行している。努力していくというのが現時点での回答。
・発生交通量の問題含め心配している。総台数の規制をしないと安全を守れない。いくら市に税収が入っても市民が命を落としてはどうしようもない。GLPの企業理念では、地域の安全安心を守るといいながら我々のはなしをきかないうちに工事着工。これでは悪徳業者との声まである。地域と一体となって経営をすすめることを含め、社長の見解を求めたい。
●武蔵野小、瑞雲中など、東側は学校が集中している。事故が起きたらどうするのか。安全性確保してほしい。ゲートは左折イン、左折アウトなのか。
→東1ゲートへの侵入は全て武蔵野通りから直進で入り、直進ででる。
●①滞留長を長くする=台数が増えても渋滞は発生しない という部分を説明してほしい。
②GLPのWEBサイトについて、日本では生物多様性保全、グローバルでは、viodiversity、 green buildingなどと明言。今回計画は方針に沿っていると考えているのか。
→①渋滞は発生しないといいきれないが、交差点需要率などの数値あり、交通計画をつくる際にはそれを使い交差点を評価する。
②日本GLP、Global GLPともにESGポリシーを提出。今回の開発でゴルフ場が緑と捉えれば減るが、開発するなかでしっかり対応していく。合致していないとは考えておらず、代官山は開発エリアにはいらず、北に公園があり玉川上水を繋ぐ。当初から配棟計画も変えた。
●工事計画について、東1ゲートをでて武蔵野通りを大半の車が通行する。武蔵野通りは道幅が狭いが拡幅はないのか。自分で測定もしたが、3車線にしてもトラック1台あたり右折する時間、信号の時間を考慮すると対応は十分ではなく、安全確保もはかれない。
→GLP関係者自ら通り、道幅をみて通行できると思った。
・住民は危険と判断している。
●多摩大橋そば在住。計画に不信。発生交通量を面積から割り出すのがそもそもの間違い。周辺道路や交通状況踏まえて割り出すべき。面積からだすからおかしなことになり、安全や生活環境が無視される。
滞留長延長で対策というが、右折車線延長すると、直線の通行に支障が生じる。信号の時間の問題もあるが、滞留長の延長は基本的解決にならない。発生交通量を減らし計画を根本から見直すべきと意見。
①アスベスト除去について、煙突の断熱材を水を使用して除去するが、水に含まれるアスベストはどのように回収するのか。
②新設道路では、歩道と自転車専用道をパイプで仕切るが、車が衝突したとき歩道に入り込まない頑丈さはあるのか。ガードレールとの違いは。
→①アスベストが含まれる部分は最終的に袋詰めして適切な場所に。含まれない部分は、含まれないことを確認してから放流。
②ある程度頑丈だがガードレールほどではない。
(その他、台数については、敷地面積ではなく、計画する建物面積から割り出す。データセンターも組み合わせた。)
●フォレスト・イン昭和館について
→土地・建物の所有は移ったが、ホテルは経営が別。集まる場として機能していたことは承知している。他地域では外に貸し出すことをしておりそうしたことは検討。