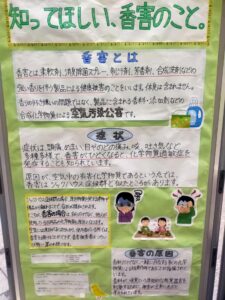公民館まつり:「公民館まんなか構想~ドイツと北欧の生涯学習事情~」
一昨日は、公民館まつりへ。
本年は、スタンプラリー用紙が「公民館のトリセツ」になっており、
公民館の機能や場所案内が書かれ、周知を兼ねている工夫が素敵!
全ての企画・展示から学びがあり、
多くの市民が関わりつくりあげていることが伝わってくる、あたたかな場でした。
実行委員に各団体の皆様には大変お疲れ様でございました。
午前は、東京大学准教授/公民館運営審議会会長 新藤浩伸先生の学習会
「公民館まんなか構想~ドイツと北欧の生涯学習事情~」にも参加。

昨年、ユネスコの生涯学習研究機関があるドイツハンブルグに滞在し、ここを拠点にヨーロッパの生涯学習の拠点を訪ねられた新藤先生は、
ドイツ・北欧の市民大学、図書館、博物館の特徴をおはなしくださいました。
○市民大学
ドイツでは年間通じて多様な講座が提供されており(ハンブルグでは対面学習によるコミュニケーションを重視しつつ2263講座)、
北欧では18~25歳程度の若者が1~2年間宿泊し共同生活をしながら、文化や社会に学ぶ場であるとのこと。
学校教育と両輪である社会教育を、いかに充実させているかが分かりました。
○図書館
子どもが育っていくためには経済状況に関わらず必要と、おもちゃやゲーム、アニメDVD等貸し出す、
語学を無料で学び合うサークル活動の支援、
楽器や楽譜の貸し出し等するハンブルク図書館や
物づくりもできたり、1日でも過ごせる親子用スペース等あるノルウェーの図書館の事例からは、公共の役割について考えさせられました。
○博物館
現在私たちが直面する答えのない問いを投げかける機能も有していました。
○他国と比較することで生涯学習をより俯瞰して捉えることができましたが、
日本の公民館の特徴は、ドイツや北欧のように提供する側に行政だけがいるのではなく、
地域住民もともに支えるという、市民参加であるそうです。
ユネスコハンドブック「生涯学習の実現をめざして」によれば
「自分のために、他人のために学び、行動することで民主主義がつくられる」
「生涯学習は民主的な地域社会の基盤をつくる」。
昭島市については、昨年9月に昭島市公民館運営審議会が
現在の時代背景から求められる公民館の役割を捉え直しつつ、
「公民館事業の基本方針に対する答申ー暮らしのまんなかに公民館をー」をだしたとのこと。
基本方針のイメージ図は共生、協働を軸に、
公民館という場を活かしきる素晴らしいものでした。
みなで公民館を活かしきりたいですね。