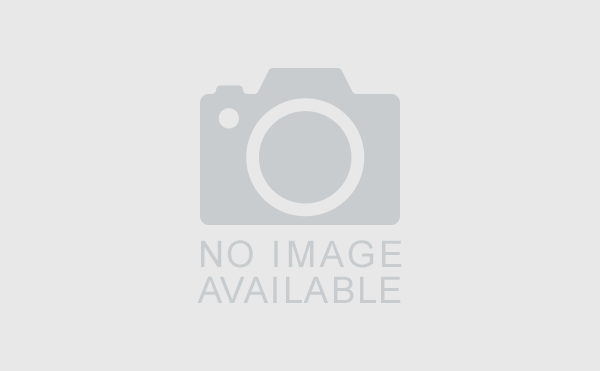2025年9月決算審査特別委員会:教育費・介護保険特別会計(包括的性教育、不登校への対応、香害、放課後子ども教室と子どもの居場所、総合スポーツセンタープール、スクールバス、国際理解、デジタル教育、介護ベッドのキャスター)
最後に、教育費・介護保険特別会計について報告します。

◆包括的性教育
○昨年のPTA企画含めた包括的性教育実施校
○現場のニーズを捉え、市としてどのような対応をしているか
質問。
包括的性教育は人権教育でもあり
全校での取り組みを教育委員会が後押しすべきです。
◆不登校への対応
スクールソーシャルワーカー(SSW)の配置人数が拡充された効果と課題を質問。
SSWは不登校に関連する課題についても伴走してくださいますが
不登校当初は SSW含めた社会資源を把握することが非常に困難とのお声をかねてから頂きます。
調布市のリーフレットなど参考に
市でも分かりやすい発信に取り組み頂きたいと質問しました。
また、多様な居場所を選択できることが重要であり
○八王子市のように、給食センターを不登校の児童生徒が給食を食べられ居場所としても機能させる取り組み
○校内別室指導支援員配置事業の継続
を求めました。
あわせてそもそも学校が子どもたちにとって居心地よい場となるよう、引き続き施行錯誤頂きたい。
◆香害
先月、香害について日本臨床環境医学会と室内環境学会が実施した全国調査結果が公表されましたが、
○学年があがるほど体調不良者は香害による体調不良者は増し
小中学生の約10%が体調不良を経験、
約2%は不登校傾向にある
○目立つのは「給食着を何とかしてほしい」という声
であったようです。
識者は「教育現場の早急な対策が求められる」とするなかで
○市はどう考えるか
○給食白衣については何度か質問している自前のエプロンとの選択制とすること
を質問しました。
◆放課後子ども教室と子どもの居場所
現場のコーディネーターから頂くお声(人手不足や報酬増)を伝え、改善の余地があるか質問。
働きやすさは子どもの居心地の良さに繋がります。
別の課題とされる場所確保については、三鷹市の「学校3部制」の取り組みを紹介しました。
また、放課後子ども教室限らず、
今後居場所全般をどうしていくのか考えを確認。
こども家庭庁の「こどもの居場所づくりに関する指針」では
子ども・若者の主体性を大切にすることや
こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくることなど述べられていますが、
この視点をぶらさず持つことが必要と考えます。
多様な居場所を拡充しながら、
すでにある居場所についても大人本位に偏らず、そのときどきの子どもとともに常によりよくしていくことは大きな取り組みですが、引き続き私も考えてまいります。
◆総合スポーツセンタープール
不具合で利用できなくなりました。
その間の市民の水泳機会の代替をどのように考えているか見解を問いました。
◆固定級・医療的ケア児のスクールバス利用
過去固定級へのスクールバス導入について質問しましたが、その後の検討状況を質問。
難しさがあるようですが、まずは当事者の状況確認を求めました。
また、医療的ケア児の移動支援のニーズは高く、東村山市など他自治体の取り組みの情報収集を求めました。
◆国際理解
日本語が不自由なお子さんへの対応を質問。
また、外国ルーツのお子さんがたと周囲との相互理解を深め
地域共生にも繋げるよう意識頂くことを求めました。
◆デジタル教育
先駆けてITを活用していたスウェーデンでは、国際学力調査での学力の急激な低下など理由にアナログに回帰しており、
ノルウエーやフィンランドでも同様の動きがあります。
デジタルには特別支援教育や不登校支援等々の観点から良さもありますが、
デジタル一辺倒にならないよう総じてどのように向き合っていくか考えを問いました。
◆介護ベッドのキャスター
運用が一部変更されましたが、市民相談を受けました。
現場にも意見をきいたのちの変更か確認をしました。